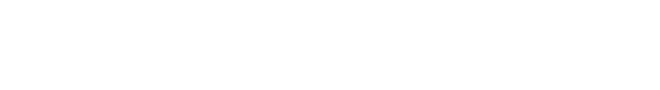内装工事関連の業務に携わっていると、防火区画を貫通して配管や通線を行わなければならない事があると思います。ただやはり“建築”の方々と比較して“内装”の方々は“防火区画”や“貫通処理”との接点が少なく、曖昧な理解のまま、なんとなく電気屋やB工事関係の方にお任せで済ませている事も少なくないと思います。
きちんとクライアントへ説明をしたり、工事関係者と対等に協議をするためにも最低限の事は知っておくと良いです。そのような観点で以下に解説したいと思います。
そもそも防火区画とその貫通処理とは?
防火区画
特定の建築物はある一定以下の面積の部屋を耐火性のある床や壁で取り囲み、そこから外に火災が広がらないようにする必要があります。その「耐火性のある床や壁で形成された区画」が「防火区画」です。つまりその部屋で火事が起きたとしても、その区画から避難さえすれば、隣の区画に炎が辿り着くまでに時間がかかるため、消火または避難の時間が確保される、という事です。ですので、当然ながら原則その床や壁を「開口」してはいけません。炎の通り道ができてしまいます。
防火区画の詳細は別の記事で解説しています。
⇒【簡単に解説】防火区画、防煙区画とは?と、その違い。
貫通処理
上述のように本来「開口」は避難安全上、望ましくないのですが、電気配線や空調ダクト等、開口して通さざるを得ない設備が存在します。そのためその開口と塞ぐ方法を法律で規定しています。その「防火区画を開口し、管や線を通して、その貫通部を炎が通らないように適切な処理をする事」を「貫通処理」と呼びます。
「防火区画の貫通処理」を経験豊富な方々は省略して“区画貫通”とか“貫通処理”とか呼ぶので、そもそも慣れていない方は何を指しているのかすらわからない事もありますのでご注意です。特に“区画”という言葉は「防煙区画」と混同しやすいのでご注意です。
貫通処理の方法はきちんと法律で定められています。ただ内装工事関連の方々が接するのはほぼ「耐火パテ」等のメーカー商品を使用した処理方法だと思います。そして、実際に火事にならないと問題が顕在化しにくいため、以下のようなら曖昧な理解やをされてる方や疑問を持った方々も多いと思いますので、その辺りもクリアにしたいと思います。
・とりあえず耐火パテで埋まっていれば良いんだよね?
・どのメーカーのものでも大丈夫?
・不燃材で塞いでも良い?
・シール貼ってあるのは何?
・とりあえず電気屋に任せよう。
貫通処理の方法
まず、法律を確認してみましょう。
建築基準法施行令
第五章の四 建築設備等第一節の二 給水、排水その他の配管設備(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第百二十九条の二の四 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
七 給水管、配電管その他の管が、第百十二条第二十項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁若しくは防火床、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(ハにおいて「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項若しくは第四項から第六項まで、同条第七項(同条第八項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第九項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第十項(同条第八項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第九項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第十八項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁若しくは防火床にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
引用:建築基準法施行令 第129条2の4第1項第七号
はい。。。読むのも条文追い回すのもとてもしんどいので、以下に要約します。防火区画を貫通する場合は以下のイロハいずれかで行いなさい、という事です。
イ:貫通する部分からそれぞれ両側一メートル以上を不燃材料で造ること。
ロ:外径が、用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ:国土交通大臣の認定を受けたものであること。
それそれ解説します。
イ:貫通する部分からそれぞれ両側一メートル以上を不燃材料で造ること。
両側1メートル以上を不燃材で造り、隙間を不燃材で埋めればOKです。


ロ:外径が、用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
つまり、用途に応じて、素材と径と肉厚を守れば、1m不燃材で造る必要はない、という事です。簡単な表にしました。

ハ:国土交通大臣の認定
大臣認定は、申請者が耐火試験を行い、評価された範囲の構造・材料・寸法どおりの条件で認められます。その認定工法は1000以上ありますので、把握することは不可能です。内装のお仕事をしていてよく見かける、または対応を求められるのは、加熱膨張材を用いるタイプと思います。事前準備と施工が比較的容易だからだと考えます。
方法を選定して施工をする際、または施工を監理(管理)する際の注意点としては、「工法通りに行う事」「シールを貼る事」です。黒いパテ材で埋まっていれば良いというとではなく、実証実験により一定時間の遮煙性能が認められてた方法で行い、かつそれを証明できるようにしておく事が大事です。状況に応じて選定をするのはかなりの知識を要しますので、リスクがある場合は、新築時の設計者が選定したものを使用する、か、設計士に依頼する、メーカーに選定を頼むなどして、専門家の判断に従って下さい。施工後は必ず認定シールを貼るようにしてください。適切に処理を行う事で法定点検の際に是正対象となることはなくなり、本来の目的である火災の際の遮炎性能が担保されます。
例えば、別の現場で余った耐火パテがあるから使っても大丈夫か?という疑問が良くあります。結論から行くとやめた方が無難です。もちろんその構造に適した耐火パテを正しく使用し、かつ認定シールを貼れば問題ないのですが、認定シールが無かったり、もとの構造と適していない可能性があるので、必ず設計者や施設管理者に確認してください。
雑学、消防法上の区画:令8区画とは?
内装工事関連の方が自分たちの判断で防火区画を開口する事はまず無いと思います。なのであまり関係ないはずなので、さらっと読んで下さい。知識として知っておくと、博識感が増します。笑
建築基準法とは別で消防法で規定されている“防火区画のような区画”があり、令8区画と言います。令8区画とは、防火対象物が「開口部のない耐火構造の床または壁」で区画されているときは、その区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなして消防用設備等の設置基準を適用できる区画のことです。そして「開口部のない」が重要な文言でして、「特定防火設備である防火戸」や「ドレンチャー設備」も、上記で解説した大臣認定工法等のいかなる区画貫通処理を施しても認められません。
建築基準法と消防法のややこしさはこんなところにもあるんだな、となんとなく知っておくと役にたつ事もあるかもしれません。