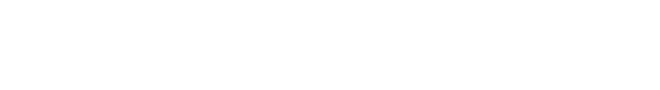軽鉄工事を知る事
軽鉄工事について解説します。内装工事はまず軽鉄工事から始まる事がほとんどです。解体工事からの場合ももちろんありますが、軽鉄工事を知らないと解体もできません。天井、壁、造作の下地になりますので、各種電気や機械設備にも絡みますし、仕上工事の下地にもなります。施工管理、設計、内装監理室などの多岐にわたる業務において、これを知らないと会話にもなりません。内装工事に関わる全ての人に必要な知識を経験を交えながら解説します。
そもそも軽鉄とは?
軽鉄は“軽量鉄骨”の略称で、軽鉄の他に“LGS( Light Gauge Steel=軽量規格の鉄)”と呼び名があります。また軽量(鉄骨)天井を“軽天”と略すこともあります。“軽量鉄骨”とは、鉄骨の中でも鋼材の厚みが6mm未満の物を指します。6mm以上の物は重量鉄骨と呼ばれ、主に建物の構造体として用いられています。軽量鉄骨下地とは、吊り天井や間仕切壁など、ボード材等を貼るための下地として、軽量鉄骨で構成された骨組を指します。厚み6㎜未満と記載しましたが、付帯する細かいパーツを除き、0.5mm~1.6mm程度の厚さです。C型鋼、あるいは中が空洞となっている角型鋼が内装材に用いられます。
軽量鉄骨の特徴
この工事が普及し始めたのは昭和50年頃と言われています。それまでは大工が木材を削って柱を一本ずつ立てるという作業でした。軽天工事が出来るようになってから、木材が不要になり、工事が大幅にスピードアップし同時にコストカットもできるようになったのです。オフィスや店舗、病院などの内装工事において非常に一般的な工事です。従来用いられていた下地材である木軸と比べ以下の特徴があります。
【メリット】
・耐火性が高い
・寸法安定性に優れる
・軽量で建物への負担が少ない
・供給が安定しており、安価
・環境に優しい
・曲げ加工をすることができる
鉄であるため、木軸と比べ火に強く、火災が発生したときの安全性が高いです。また、木は湿気により反りや膨張収縮が発生しやすいですが鉄ではほぼ発生しません。低コスト・短工期で施工できるため、以前主流だった木材を使用する下地工事に代わり近年主流となっています。また、リサイクル可能な環境にやさしい下地材でもあります。
【デメリット】
・規格が決まっているため現場での寸法の微調整が難しい
軽鉄間仕切り工事の施工方法
①墨出しを行う
軽鉄の施工を始める前に、設計書や施工図通りに、壁下地材の芯墨(しんずみ)や逃げ墨(にげずみ)などの墨出しを行います。墨出しの解説は別の記事で解説しています。⇒墨出し
②上下ランナーを固定する
天井と床にランナーを固定していきます。ランナーは、スタッド(間柱)を垂直に立てるためのレールのようなものです。墨に合わせてランナーを設置し、打込みピンやタッピングビス、溶接などで固定していきます。ピンの固定には、火薬を使用しないガス式鋲打機(がすしきびょううちき)やガスネイラがよく使用されています。主流はHILTI(ヒルティ)というメーカーのもののため、現場では「ヒルティ」と呼んだり、「てっぽう」と呼ぶ職人さんもいます。
空港の工事で入館する際の手荷物検査時に「このケースにはいってるのは何ですか?」と聞かれ、純粋無垢な職人さんが「てっぽう!」と答えて大騒ぎになったのも今は昔です。
③スタッドを切断する
スタッド(間柱)は、壁の高さに合わせて切断します。スタッドを切断するときは、高速カッターを使用すると精度よく加工できます。また、高速カッターを使用すると、切断面に亜鉛めっきの犠牲防食作用(ぎせいぼうしょくさよう)が働くため、防錆塗装(ぼうせいとりょう)が不要になります。犠牲防食作用とは…傷がついて鉄が露出したときに、亜鉛が鉄より優先して溶け、鉄の腐食が進行しない状態のこと。但し火気作業になるため、現場によっては利用できない場合があります。その場合はプレカットするか、バンドソーで切断するなど工夫が必要です。
④スタッドを設置する
スタッドのピッチは、張り付ける石膏ボードの枚数で異なります。1枚の場合は450㎜くらい、2枚の場合は300㎜くらいの間隔で設置していきます。スタッドの役割には、地震時にスタッドとランナーのズレでショックを吸収し、石膏ボードの破損を防ぐというものもあります。そのためスタッドは固定せずに、動くようにしておくのが正しい状態です。
⑤振れ止めを取り付ける
振れ止めは、スタッドの揺れを防止するための材料です。
⑥開口部を補強する
開口部には、補強材を取り付けます。
・出入り口、建具枠、窓等の開口部の補強
・ダクト類の開口部の補強
ドアや窓などの重さや振動、衝撃などが加わるため、出入り口や窓には補強材を使用します。垂直方向の補強材は、スタッドに抱き合わせて溶接します。このとき、端を押さえて600㎜程度のピッチで溶接し、組み立てたものを使用します。また、溶接箇所には、防錆塗料を施しましょう。ダクト類の開口部の補強には、使用した種類のスタッドやランナーを活用します。上下枠補強材はスタッドに取り付け用金具を、縦枠補強材は上下枠補強材に取り付け用金具を、溶接や小ねじなどで取り付けます。また、振動や音が発生しないように、ダクト類が下地に直接触れないように施工するのも重要なポイントです。
工事中の火気に注意
LGSの加工をする際、必ず火花がでる作業をしなければなりません。火花が他に飛び散らないように養生しましょう。飲食店の工事等の場合は近くにガスボンベや引火性のものが近くにある場合は加工場所を遠ざけるか、引火物を遠ざける必要があります。最新の注意を払う必要があります。 場所や部材によってサビが発生する可能性あり、軽鉄材は溶融亜鉛めっきと言ってサビに強い加工がされていますが、海の近くや極端に湿気が多いところでは錆が発生します。その他にも加工した切り口の防錆塗装を怠っていたり、違う金属同士が触れ合うことで起きる「電蝕」によって軽鉄材の一部分だけが激しく錆びて弱くなることがあります。対策としてステンレスのLGSを使うことがあります。加工後防錆塗装をする必要がありません。細かい部品やビスをすべてステンレスにすることで「電蝕」を起こすリスクもなくなります。その代わり金額が2倍以上に上がる事があります。